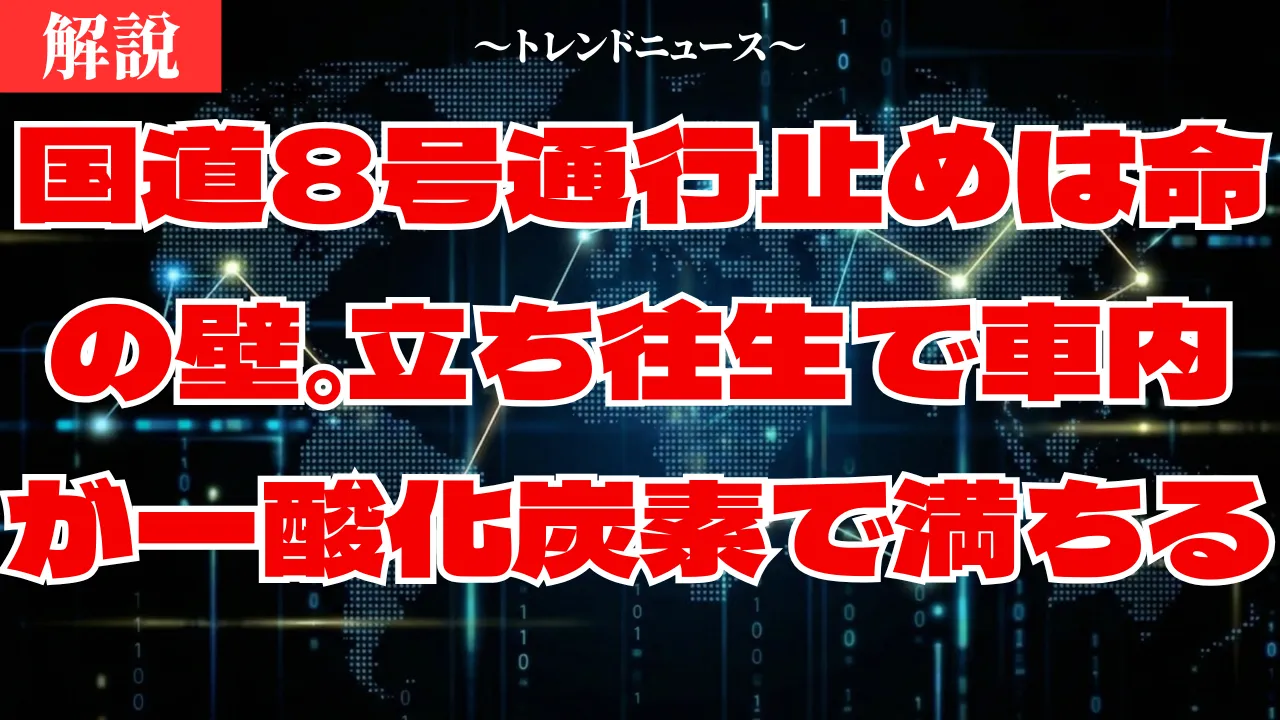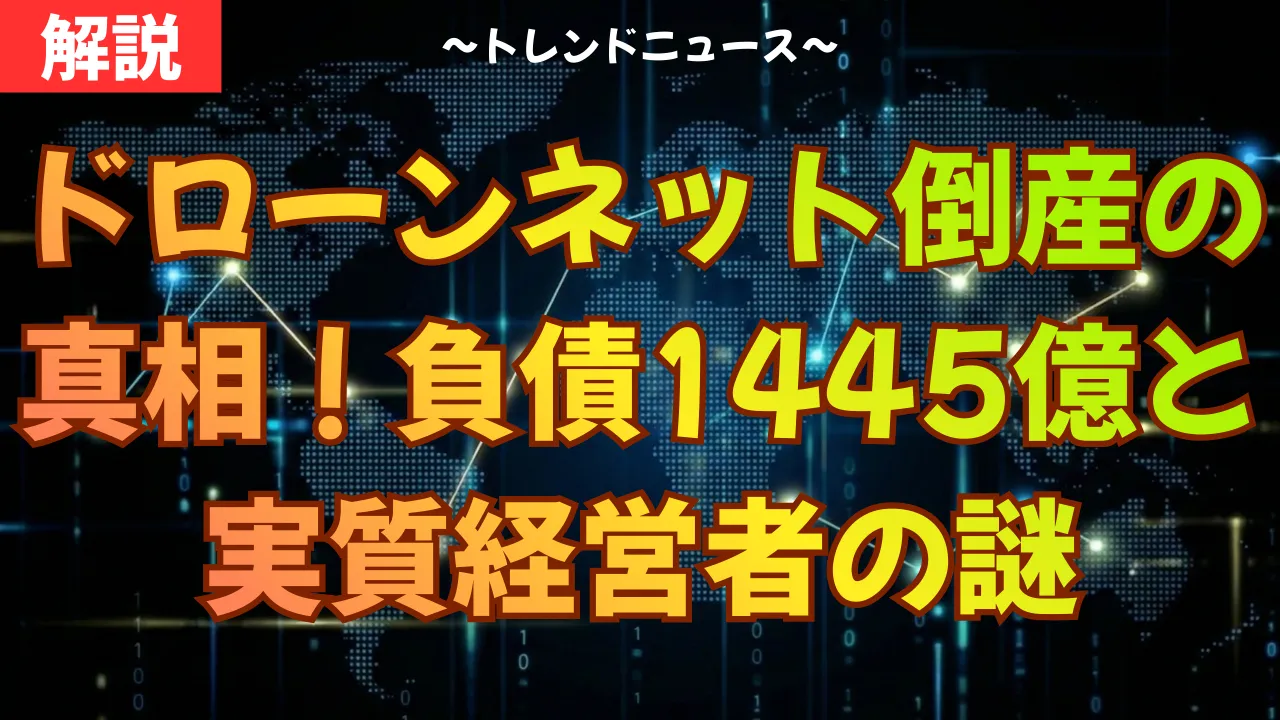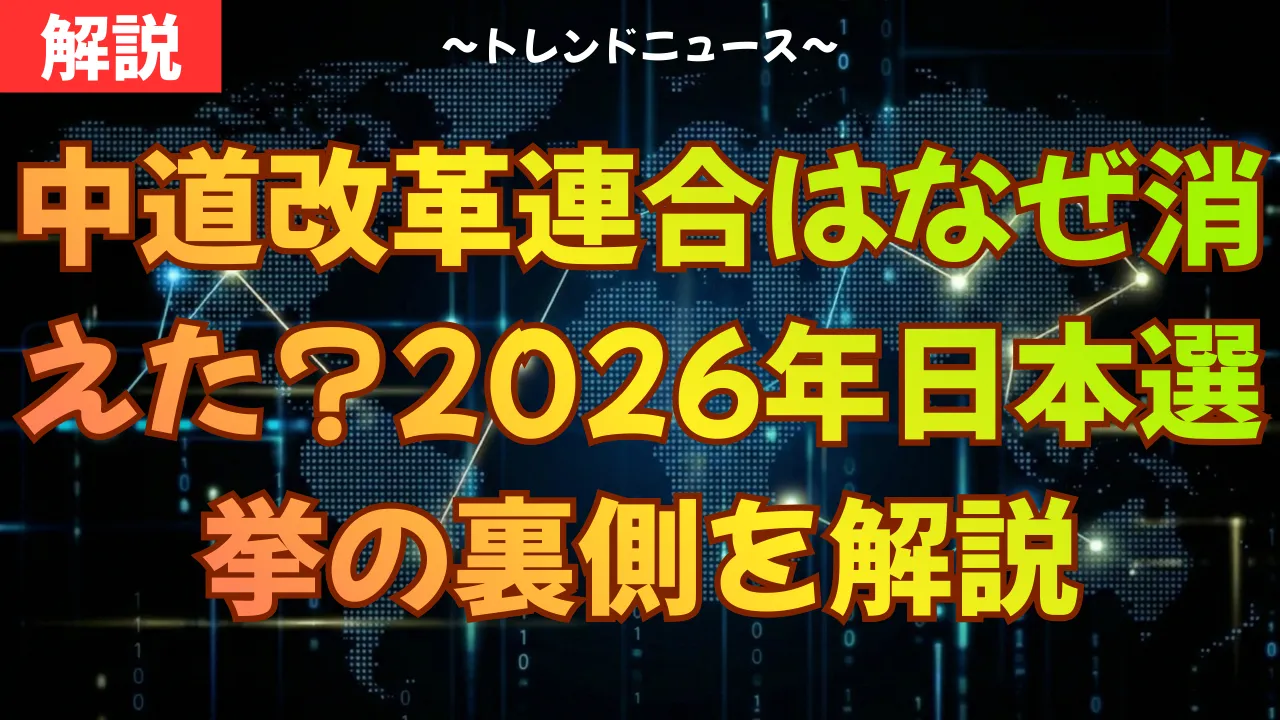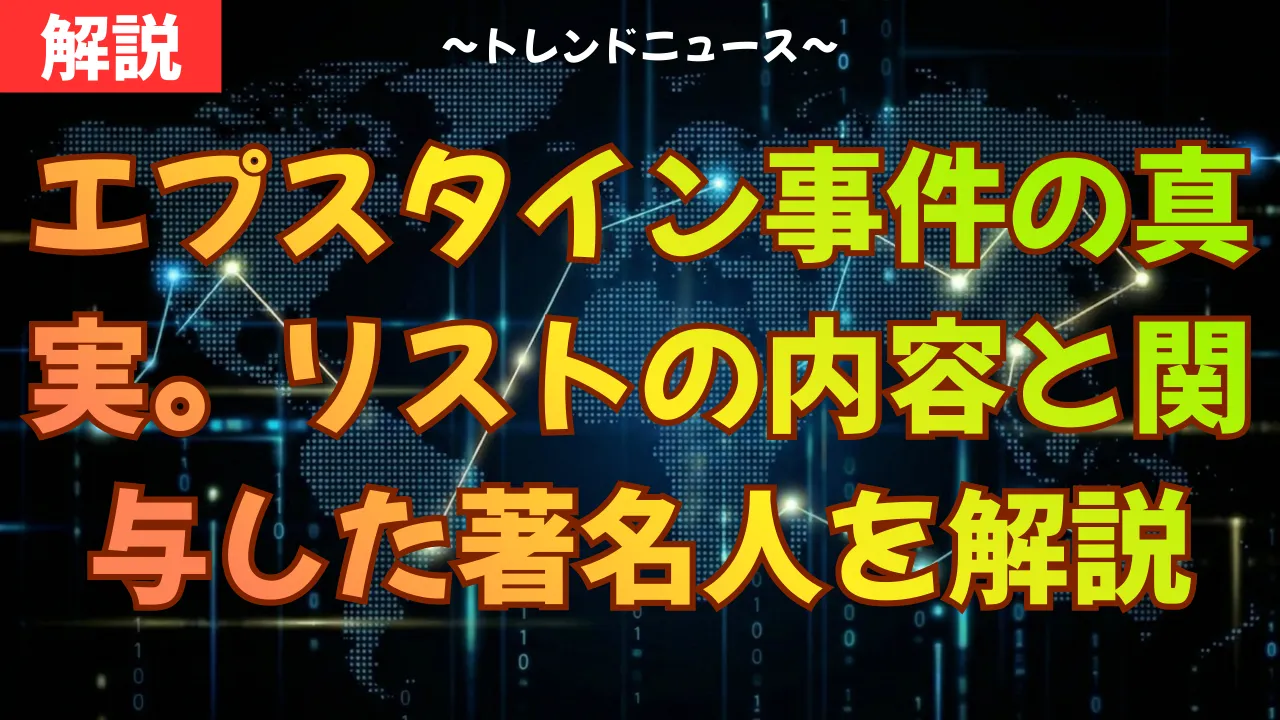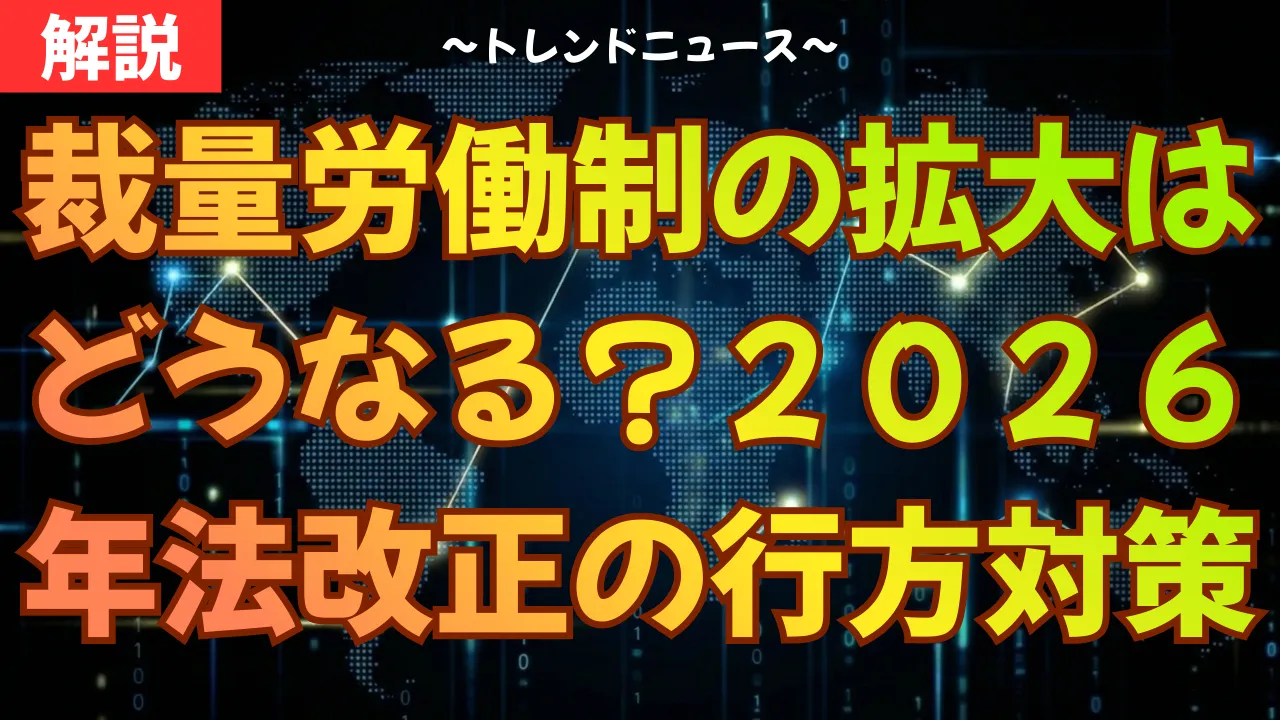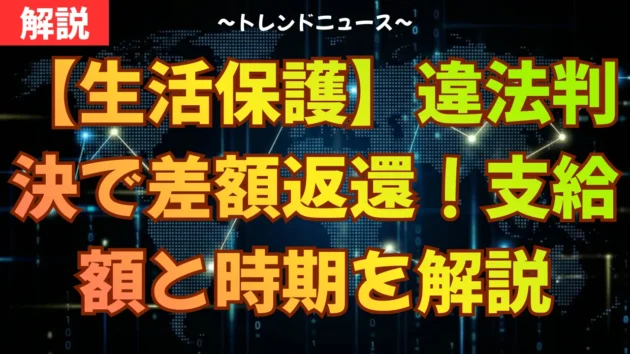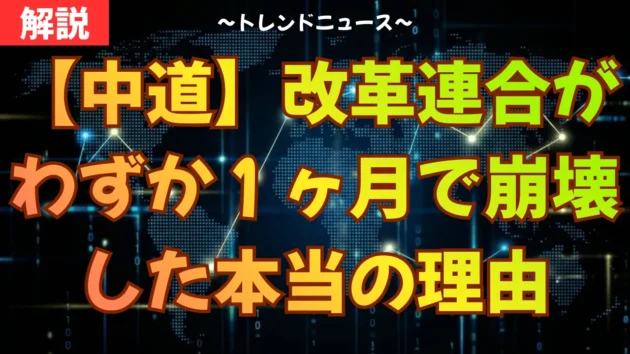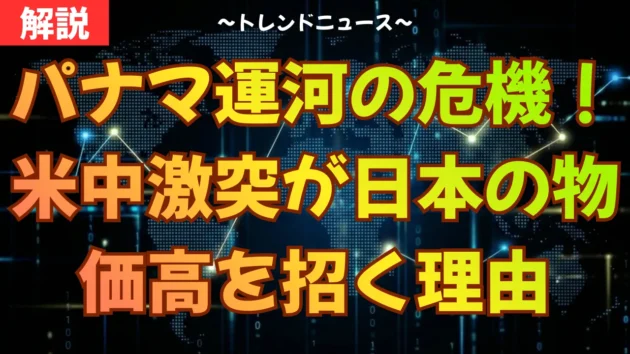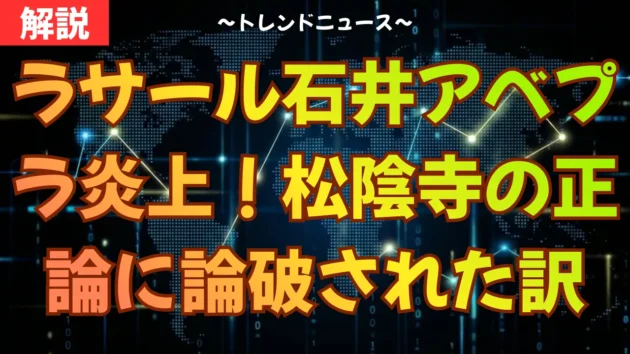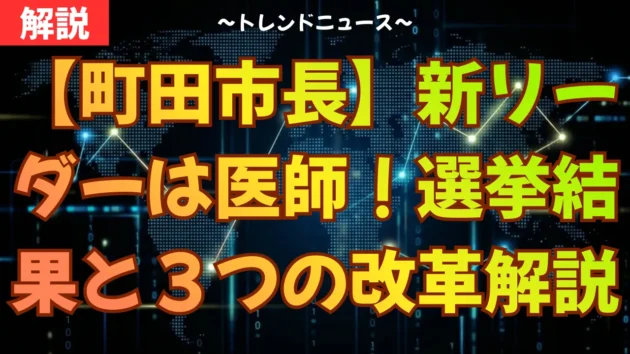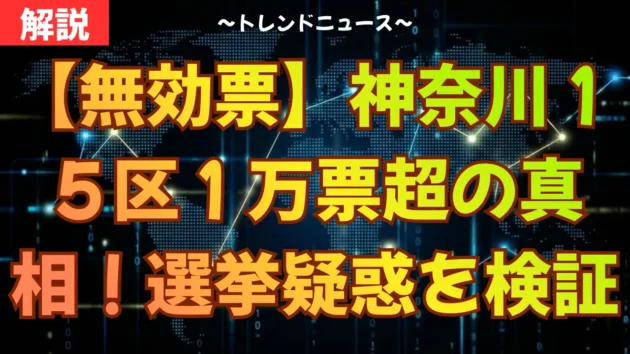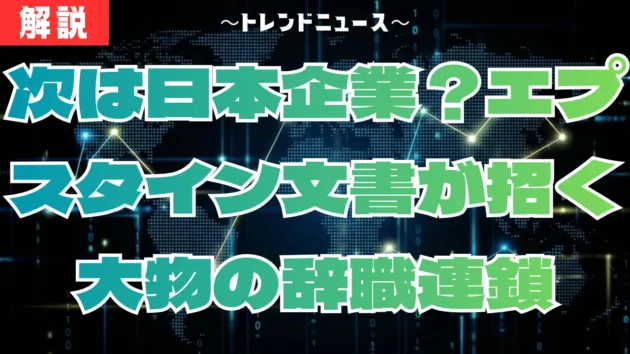2026年に入り、私たちの働き方を大きく左右する「裁量労働制」の議論が再び熱を帯びています。昨年末には一度「労働基準法の改正見送り」と報じられましたが、年が明けてから高市首相や経団連が「適用拡大」に向けて強力なプッシュを続けているからです。
「結局、法律は変わるの?」「自分の仕事も対象になるの?」と、現場の人事担当者やビジネスパーソンの間では不安と疑問が交錯しています。ニュースの見出しだけでは、実際の企業活動にどう影響するのかが見えにくいのが現状でしょう。
そこで本記事では、2026年2月時点の最新情報を整理し、経団連が提案する「労使自治による対象業務の拡大」の中身や、現在行われている労働政策審議会での激論のポイントについてわかりやすく解説します。今後の法改正に備え、企業が今知っておくべき実務の課題を一緒に見ていきましょう。
2026年「裁量労働制」法改正の最新動向とは
2025年の年末、多くのメディアが「労働基準法の改正案提出を見送り」と報じたことを覚えている方も多いのではないでしょうか。しかし、2026年を迎えると状況は一変しました。高市首相が施政方針演説などで、働き方改革の一環として「裁量労働制の見直し」に強い意欲を示したのです。
この動きの背景には、経済界からの強い要望があります。政府としては、労働基準法全体の抜本的な改正には時間がかかると判断しつつも、成長戦略の鍵となる「規制緩和」、とりわけ裁量労働制の適用拡大については先行して議論を進めたいという意図が見え隠れしています。
つまり、「全体的な法改正は少し先になるが、裁量労働制のルール変更だけは急ピッチで進む可能性がある」という非常に流動的な局面にあるのです。企業としては、単なる先送りだと安心せず、この政治的な揺り戻しを注視しておく必要があります。
経団連が求める「適用拡大」と「労使自治」の提案内容
では、使用者側である経団連は具体的にどのような制度変更を求めているのでしょうか。最大のポイントは、対象業務を法律で細かく決めるのではなく、それぞれの企業の事情に合わせて決められるようにする「労使自治」の重視です。
現在、裁量労働制を導入できるのは、法律で定められた特定の業務に限られています。しかし経団連は、「過半数組合などとの合意(労使協定)があれば、企業が主体的に対象業務を決められるようにすべき」と主張しています。これは、急速に進むDXやイノベーション創出に対応するため、より柔軟で自律的な働き方を可能にしたいという狙いがあるからです。
また、日本企業で導入が進む「ジョブ型雇用」との親和性も無視できません。成果や職務内容で評価するジョブ型と、労働時間ではなく成果で評価する裁量労働制はセットで語られることが多く、労働生産性を高めるための重要なツールとして位置づけられています。
労働政策審議会での激論|連合(労働側)が反対する理由
一方で、労働者側を代表する「連合」は、この適用拡大に対して慎重な姿勢を崩していません。厚生労働省の労働政策審議会では、経営側と労働側の意見が真っ向から対立し、激しい議論が繰り広げられています。
労働側が反対する大きな理由は、「2024年4月に行われた制度改正の検証がまだ不十分である」という点です。つい最近、本人同意の手続きや健康確保措置が強化されたばかりなのに、その効果を見極めないまま対象業務を広げれば、なし崩し的に長時間労働が助長されるのではないかと強く懸念しています。
また、各種実態調査において「裁量労働制といきながら、実際には十分な裁量が与えられていない」というデータがあることも、反対の根拠となっています。両者の主張の隔たりは大きく、議論の行方は予断を許しません。
【経営側と労働側の主張対比】
| 項目 | 経営側(経団連など)の主張 | 労働側(連合など)の主張 |
| 適用拡大 | イノベーション創出のため、対象業務の拡大が必要。 | 長時間労働を助長する恐れがあるため反対。 |
| 決定プロセス | 法令による限定ではなく、労使協定(労使自治)に委ねるべき。 | 労働力の立場の弱さを踏まえ、法令での規制が必要。 |
| 制度の評価 | 柔軟で自律的な働き方が可能になり、生産性が向上する。 | 実態調査では「名ばかり裁量」のケースも多く、過労死等のリスクがある。 |
| 優先順位 | 変化の激しい時代に対応するため、早急な規制緩和を。 | まずは2024年改正ルールの定着と、健康確保措置の徹底が最優先。 |
裁量労働制「専門業務型」「企画業務型」の現行ルールと課題
現在の裁量労働制は、利用できる仕事の種類が法律で非常に厳しく制限されています。労働者を過労から守るため、本当に時間配分のコントロールが必要な職種だけに絞り込んでいるからです。
具体的には「専門業務型」と「企画業務型」の2種類に分けられています。専門業務型はエンジニアや研究職など、国が定めた20の業務しか対象業務として認められていません。企画業務型も、本社機能の中枢部門で事業運営の企画を行う一部の社員に限定されています。
そのため、近年急増しているDX推進の担当者や、新しいビジネスを立ち上げる職種などには適用しづらいのが実情です。経営側からは、労働基準法の古い縛りが事業成長やイノベーションの足かせになっているという不満の声が上がっています。
適用拡大が実現した場合、企業実務はどう変わる?
もし経団連の要望通りに適用拡大が実現した場合、企業が対応すべき実務は大きく変わります。国が対象を決める方式から、企業ごとの話し合いでルールを決める方式へと責任が移るためです。
制度の利用を広げるためには、これまで以上に社内の過半数代表者や労働組合との丁寧な合意形成が重要になります。同時に、以下のような実務負担が増えることも覚悟しておかなければなりません。
- 社員との定期的な面談など労使コミュニケーションの強化
- 勤務間に一定の休息を設けるインターバル制度の導入
- 客観的なデータに基づく健康確保措置の徹底
企業は単に対象者を増やすだけでなく、社員に自律的な働き方ができているかを確認する義務があります。名ばかりの制度にならないよう、労働時間を正確に記録し、適正運用を証明する仕組みづくりが不可欠です。
まとめ:今後の議論のスケジュールと企業がすべき準備
2026年以降も法改正に向けた議論は続きますが、企業は今すぐ足元の準備を整える必要があります。適用拡大の実現は早くても2027年以降と予想されるものの、まずは現行ルールの徹底が強く求められているからです。
とくに2024年の改正により、対象者からの本人同意の取得や、同意を撤回した際の記録の保存が厳格化されました。これからの時代は、労働基準法に則った正確な時間管理と、透明性の高い手続きが企業の信頼を左右します。
将来の法改正にスムーズに対応するためにも、まずは自社の勤怠管理のあり方を見直すことから始めてみてください。複雑な手続きや労働時間の集計をミスなく行うために、最新の法改正に自動対応できる専用システムの導入をおすすめします。